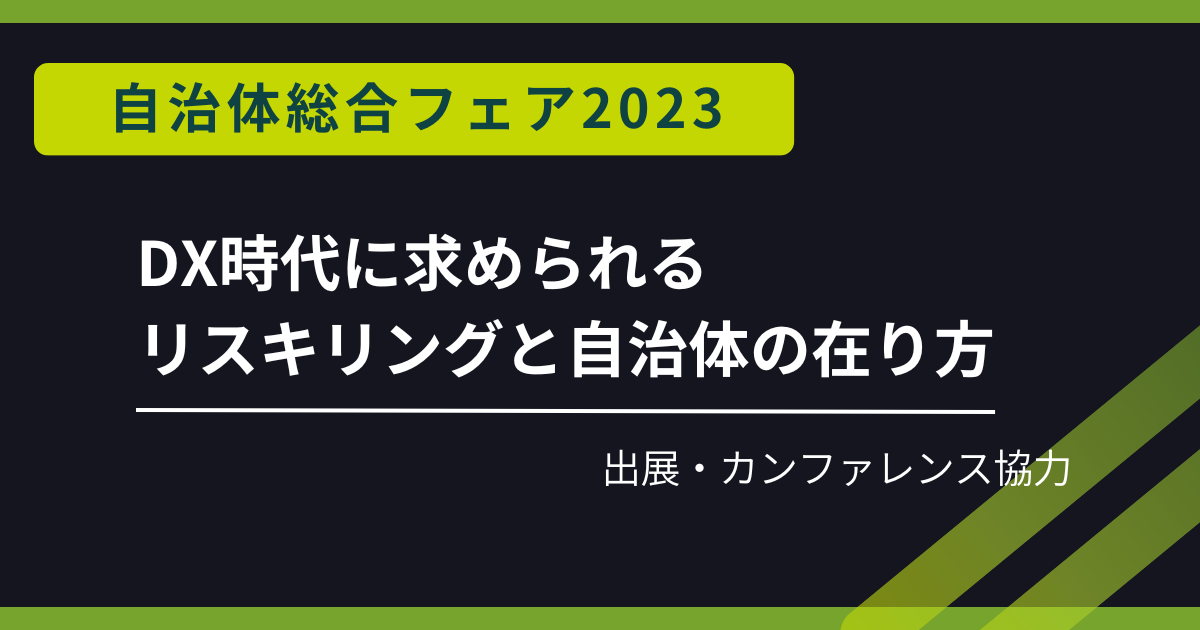社会活動から大学へ、さらに国の中枢へ
#ホンネのDX 今回は地方自治体のデジタルトランスフォーメーション推進に係る検討会座長、庄司昌彦さんとの対談です。
庄司さんは大学で教鞭をとるかたわら、総務省の地域情報化アドバイザーをはじめさまざまな役職で活躍されています。また、とあるアーティストとして創作を楽しむ一面も持っています。
そんな庄司さんに、大学での研究に至った経緯や、教育や地方自治体DXの標準化等の取り組みを通じて叶えたい未来についてホンネを伺いました。
扇の要になれる人をつくる
菅原:いつも私のほうから他己紹介という形でご紹介をさせていただくところから始まるんですけれども、ではご紹介させていただきたいと思います。
まず1点目、庄司さんは武蔵大学の社会学部メディア社会学科の教授であり、情報社会学、地域の情報化、電子行政といった分野がご専門です。
2点目は、数えきれないくらい多くの委員やアドバイザーをなさっているということで、主だったものだけでも、総務省の地域情報化アドバイザー、仙台市のような大きな自治体の情報アドバイザー、自治体のシステム標準化検討会の座長から、地方自治体のDX推進に関わる検討会座長まで、まさに日本国中のDXの中心的なところを担っていらっしゃいます。
3点目が、一般社団法人オープン・ナレッジ・ファウンデーション・ジャパン代表理事。
これだけのさまざまな肩書を持っている中で、ご趣味は「ケチャップアート」なんですね。私からの紹介はこのあたりでとどめて、自己紹介もかねて補足をお願いできますか。
庄司教授:ありがとうございます。最初にご紹介いただいたように、東京の練馬区にある武蔵大学で社会学部の教員をしています。グローバル・データサイエンスコースの主任をやっていまして、学生たちに、英語を使うこととデータサイエンスの手ほどきをしています。
自治体でもそうだと思うんですけども、データサイエンスと言うとすごく遠い世界のものだと思う人も多いと思います。でも、データ分析者でない人文系学部の人であっても、社会の中でどこを動かすとデータが生きるか、どうやったらいいデータを作れるのかなど、考えなければならないことはたくさんあります。僕は「編集者」という言い方をしているんですけども、いろんな人がデジタルやICT、技術とかデータを使う上で、人と人をつないで、コラボレーションして、その人の良さを引き出していいものを仕立てるというような、扇の要(かなめ)になれる人を作ることを目指しています。
研究については、もともと民俗学や文化人類学といった土地のにおいがするものが好きで、地域のことは地域でやるのが大事だよねという立場で、情報通信技術に片足をおいて研究をしています。大学に来る前は、国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)という大学付属のシンクタンクにいまして、社会を運営するところで自分の力を発揮したい、貢献したいと、社会活動を先にやっていたら研究者、教員になったという感じです。
ケチャップアートは、子供が卵を食べるのが好きで、アニメや絵本に出てくるキャラクターを子供のために描いていたんです。僕は工作や絵を描くのが好きで、やっているうちにケチャップを細いチューブに入れ替えて本格的に描くようになりました。描いたものをたまたまツイッターに上げたら周りにウケがよくて、ケチャップアーティストと名乗ってみたのが知られるようになった経緯ですね。
菅原:そうなのですね。非常に多才ですね。
地域のことは地域で解決できるように
菅原:先ほど、社会活動からアカデミックの方に行かれたと伺いました。米国などでは実業とアカデミックを行ったり来たりされる教員の方もいらっしゃいますが、日本だとまだまだ珍しいのかなと思います。そういった活動をされてきたということは、目指すものやこういう社会を作りたいという強い思いがあると思うのですが、先生の目指されている世界観というのはどういったものでしょうか。
庄司教授:地域社会がその土地にある資源、つまり人、物、情報の力を十分に活用して、自分たちの地域のことは自分たちで課題解決していく社会にできるといいなと考えています。自分たちの地域のことは自分たちがよくわかっているはず、他の人にやってもらっても最終的には納得感が得られにくい。自分たちが納得して生きていくためには、自分たちのことはなるべく自分たちでやれるようにしていく、自分たちで運営するということが大事だと思うんです。
なぜそう考えるようになったかというと、母が民芸品が大好きで、家の中に置物やお面など全国のいろいろなものが飾られている家で、その土地の匂いがするもの、個性が表れているものは素敵だなと思いながら育ってきました。大学で地域ごとのローカルルールについて勉強して、なるほど、そう考えるとそうなるのかと学ぶことがたくさんあり、自治のようなことって大事だなと思うようになったのが根っこになります。ですから、基本的には誰かにお任せしてというより「自分たちでやっていく社会」というのが、実現したい世界観です。
菅原:逆に言うと、今も地域によってはそこが弱い部分もあると現状認識されているということですか?
庄司教授:そうですね。地域によって事情はバラバラだと思いますが、たとえば東京とのつながりをすごく大事にしすぎていると感じたり、地域にいいものがいっぱいあるのに東京の企業を誘致しようというのは本当にいいのかなと思うところがあったりしました。また、現在、国のDXを議論する会議の座長をしていて、こうすればよいはずだと思い切って一律にデザインすることの良さもあるのでしょうが、その乱暴さがひっかかることもあります。
デジタル技術はエンパワーするための手段
庄司教授:修士論文のテーマが介護保険制度だったんです。介護保険制度というのは、基本的な部分は国で一律に設計されながら、地域で独自に上乗せしたり別のものを加えたりする余地も残っているんです。ナショナルミニマムとして守るべきもの、維持したいものについては国が一律でベースを作るけれども、地域の事情に合わせて調整する部分も必要だよねというつくりで、これからの制度はこのように変わっていくのかなと思ったのが、大学院から社会に出てくるところでの自分の問題意識でした。そこからずっと今に至っています。
菅原:たしかにそうですね。標準で共通した最低条件があって、あとは地域の中で決める。これは介護保険の分野であっても、今先生のやっていらっしゃるデジタルであっても、基本的なコンセプトは同じなんだろうと思うんですよね。
庄司教授:はい。
菅原:最近地域に関わっていて思うのですが、地域の中で考える力というものが弱っていて、国や都道府県に「もう決めてよ」と任せるしかないような状況があるかと思います。情報通信技術を使って補完できる部分があるでしょうか。
庄司教授:まったくそうですね。情報通信技術は、英語でエンパワー(Empower)と言いますが「人に力を与える」という特徴を持っています。ひと昔、ふた昔前なら動画を撮ってインターネットでつないで、こうして生でやりとりをすることはできませんでしたよね。今はスマホでもできるわけです。これは人に力を与えている、エンパワーしているということですが、基本的にはそうやって情報通信技術は人に力を与えるものだと思います。
でも、さっき菅原さんがおっしゃったように、電子行政について担当を説得できないから、国で法律を作ってくださいよ、強制してくださいよ、と言われることがあって、本当に残念なことだという気がしてしまうんですよね。今は国のほうのルール作りのお手伝いをしているんですけども、むしろ地方からもっと独自にやりたいんだという反発を受けながら、国と地方の間のちょうどいいところを探るくらいが僕としては理想なんです。
菅原:今、すごくいいお話をお聞きしました。エンパワーという言葉は僕もソーシャルワーカーなのでよく使いますが、まさにデジタル技術というのはエンパワーするための手段なんですよね。
次回は、デジタル改革を進める上での苦労とは
庄司昌彦さんとの対談は次回に続きます。
次回は、庄司さんの関わる自治体のデジタル改革の取り組みについて、具体的な内容や目指す姿を伺います。